「ゆっくり、いそげ」
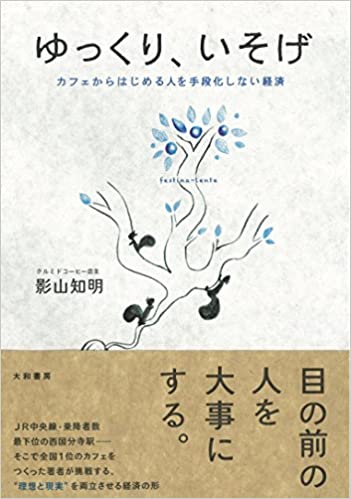
2年前、東京から鎌倉に引っ越してきてから「合理性ってなんだろう」と自問することが増えた。
朝採れたての旬の野菜しかない市場(だから冬にキュウリを買いに行っても買えない)。自家精米機を備えた、18時には閉まってしまう米屋。12分に一本しか走らない江ノ電。
いや、東京に住んでいて「合理性ってなんだろう」と思ったから、とりあえず鎌倉に引っ越してきたのかもしれない。
そんなとき、勧められてこの本を読んだ。
正直、表紙を見て「あー、こだわりのカフェ店主の身辺エッセーね」と思って、しばらく積ん読にしていた。アホでした。
著者はマッキンゼー、ベンチャーキャピタルを経て、西国分寺の人気カフェ・クルミドコーヒーを経営している。
もちろんカフェ経営についても書かれているが、これは、新しい経済についてのマニフェストだと思う。あるいは、グローバル経済とは別に、カフェに限らずなんらかの形で、ファンコミュニティをつくりながら、ビジネスをしたい人のための教科書だ。
交換を不等価にする
一番面白いと思ったのは、ここ。たとえば、著者のお店では、割引チラシやポイントカードをやらない。なぜか。人には「消費者的な人格」と「受贈者的な人格」の両方があって、「受贈者的な人格」スイッチを押すことが大事と考えているから。
そう書くと小難しいのだけど、要は「もっとくれ」じゃなく「もらいすぎちゃったな」という関係をどれだけ積み重ねていけるか。それが財務諸表に載らない、見えない「看板」になるという。
店内でのコンサートを投げ銭でやっていたとき、お客さんがなかなか増えなかった。なぜか。著者は考えて、こんな仮説にたどり着く。「ああ、毎回毎回”精算”されてしまっているのだ」と。で、定価に戻すことで「もらいすぎちゃったな」と思ったお客さんの次回参加や口コミが広まって、結果的にお客さんが増えることになる。
この本とは別だけど、知り合いから以前、こんな話を聞いたことがある。「ファイナンスの語源はファイナライズ(finalize:終わりにする)ことだ」と。
お金による取引は、とても便利だ。それは、顔が見えないから。そして、一回ごとに取引が終了するから。対照的なのは、近所のおばちゃんから取れすぎた柿とか大根をもらうことかもしれない。そこで500円払って終わりにはできない。次になにかをお返しする。その関係性が続いていく。ちょっと面倒でもあり、顔が見える安心感もある。
あえて「交換を不等価」にすることで、得られるリターンなり、ブランドがある。いや、もともとそうだったのかもしれない。
「顔の見える経済」が成立するには、どの程度の規模が必要なのか?
そうした「顔の見える経済」を、著者は「特定多数経済」という。不特定多数でもなく、特定少数でもない、経済が成り立つ規模の「顔が見える」関係性の規模を考える。
それは「5000人ほどではないか」という。クルミドコーヒーでは、この数字が3000人を超えたあたりから、経営の帳尻が合うようになってきたそう。
そして、お店として取り組んでいる出版についても、この数字がひとつの収支水準になったという。
コンサルからベンチャーキャピタルというバックグラウンドもあるのか、資本主義を否定せず、むしろ良いものとする著者のスタンスが良いなと思う。高品質のコーヒーを出しても、良質なコミュニティがあっても、収支が合わなければ仕方ない。そこで疲弊してしまうスモールビジネスも多いと感じる。でも、ミニマムでどのくらいのファンを獲得すればやっていけるのか、商圏を広げることに力を割かれなくていいのか、定量的な分析は重要だと思う。
「人に仕事をつける」のか、「仕事に人をつける」のか
クルミドコーヒーでは、以前、ビーフシチューを提供していたという。クリスマスシーズン限定のそのシチューは、とても好評で、売上増にも大きく貢献していたのだが、シチューをつくる川上さんの退職に伴って、提供をやめてしまう。
普通だったら、誰かがレシピを引き継いで、提供し続けるだろう。でも、それをしなかった。それは川上さんがつくるものだったから。
最終的にそれを受け取った人を癒し、鼓舞しうるのは、技術や知識ではなく、哲学や価値観ですらなく、それをつくり続ける人の存在だと思うからだ。
たとえば、会社経営だったら。まず事業があって、それから必要人員を割り出す。それは「仕事に人をつける」ことだ。それは、人は「替えのきく」存在ということでもある。
そう思うから、クルミドコーヒーでは「人に仕事をつける」。それぞれの人生から必然性をもって立ち上がってくる動機に機会を与える。
どちらが正解なのだろうか。少し前なら「仕事に人をつける」のがあたりまえだった。
ビジネスというのは、巨大なシステムで、人はその歯車だった。けれども、システムだけでは立ち行かなくなってきて、このクルミドコーヒーのように「人に仕事をつける」ことが大事とされる価値観の転換期に私たちは立っているのではないだろうか。
作中の短いコラムでは、ミヒャエル・エンデの『はてしない物語』が引用されている。夢溢れる想像の国、ファンタージェンが「虚無」に侵食される危機に見舞われたとき、「虚無」に打ち勝つ方法はただひとつ、「名前をつける」ことだった。
経済は、本来の「経世済民」という意味を遠く離れて、巨大でシステマティックなものとなった。サプライチェーンは長ければ長いほど、GDP増大に貢献し、誰がつくったかわからないものを食べ、代替可能な人として働くのがあたりまえだった。
「名前をつける」こと。顔の見える取引を増やしていくこと。交換を不等価にすることで、関係性を築いていくこと。
GAFAに代表されるグローバル経済は、これからも間違いなく拡大していくだろう。けれども、その一方で、こうした経済がかたちをとり始めていることを、この本でも、生活のあちこちでも感じずにいられない。


