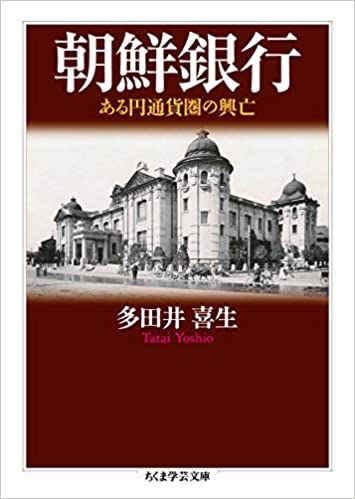金融と通貨政策から見た日本近代史 『朝鮮銀行』
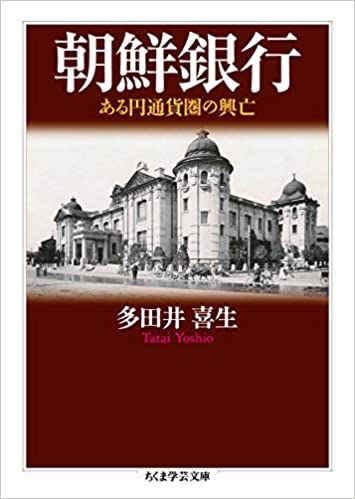
この本、面白かった。副題に「ある円通貨圏の興亡」とある通り、明治42年に設立され、昭和20年、終戦とともに日本人の手から経営の離れた朝鮮銀行の経営を通じて、日清・日露戦争、満州事変、日中戦争、太平洋戦争まで、朝鮮半島と中国大陸における通貨政策が語られている。
戦争というと武力抗争を思い浮かべるけれども、その裏にあるのは金融戦争だったりする。戦費調達が勝敗を左右する重要な要因であることはもちろん、どの通貨を流通させるかという争いがそもそも戦争の端緒になったり。
秦の始皇帝が度量衡の統一を行い、貨幣や測量の単位を定めたように、支配者がまず行うのは単位を決めることだった。租税のしやすさもさることながら、単位とはルールそのものだから。
戦前の日本が朝鮮半島や満州でどのように円を流通させようとしたのか。経済的併合と植民地経営権を巡るロシアやアメリカとの攻防。逆の立場から見れば、他国の貨幣単位を受け入れることで、どのように支配され国富を搾取されるのか、思い知らされる。
数年前、中国・山西省を旅行した時のことを思い出した。北京から時速300kmの新幹線で3時間半。かつて華北の金融を支配し、清朝時代には山西商人たちが金融業を独占していた都市。省都の太原は、日中戦争の後期、日本軍に占領されていた。
なぜ日本はここまで辿り着くことができたのか。そして支配は長く続かなかったのか。一緒にいらした方に伺うと「点は押さえられたけれども、面は押さえられなかったということです」とおっしゃった。
それは軍事力で一時的に占領し、通貨を発行することはできても、その後の経営ができなかったということなのだろう。通貨を支配することは、発行権や取締権だけでなく、国としての信用力、あるいは金融や産業政策を通じて、民衆を食わせ続けること。そのマネジメントが揃って、初めて「面を押さえた」ことになる。
かつての壮大なプロジェクト、その成れの果て。感傷的になることも、善悪で論じられることもなく、事実と数字の積み重ねで精緻に語られている。