「慈悲深き神の食卓 – イスラムを『食』からみる」
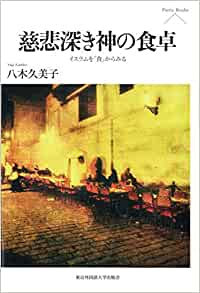
イスラムについて自分が知っていること。コーラン。礼拝。ブルカやニカブと呼ばれる衣装で顔や身体を覆った女性たち。それから、ラマダーンと呼ばれる月に行われる断食。酒や豚を禁ずる食文化。
この本は「食べる」という切り口からイスラムの世界を紹介している。テーマは、あくまで「食」だから、コーランの教えも、アラビア半島の歴史についても、必要最低限の解説にとどめ、ムスリム(イスラム教徒)がなにを食べ、なにを食べないかということにページを費やしている。だが不思議なほど、その切り口から、ある宗教がなにを教え、どのようなアイデンティティを持ち、文化や習慣を育んできたのかということが立ちのぼる。
たとえばラマダーン月の断食。一ヶ月間、日の出から日没まで、食べることも、水を飲むこともできない。
その有名な風習について、とても禁欲的な印象を持っていた。
けれども実は、ラマダーン月には、いつもより食費がかさむという。その理由は、日の出から日没までは断食するけれども、日が沈み断食が解けた後は、イフタールという断食を解く食事をとる。イフタールは家族や仲間とともに囲むことが望ましいとされ、いつも以上に豪華な食事をとることが多いからだという、
日本にいれば、夜明け前から日没まで飲食を絶ちながらも普段通りに仕事するという苦行の月でしかないラマダーンも、エジプトでは独特の味わいと華やぎのある特別な日々である。日が沈んだ後の街はランタンの灯りに照らされ、真夜中を過ぎても買い物やカフェのおしゃべりと楽しむ人々でごった返している。
まるで食のエッセーのように鮮やかで美味しそうな描写。アラブの作家たちからの引用も多く、イスラムの食文化の絢爛さがありありと伝わってくる。
そして、この本の真髄はそれだけではなく、「食べる」という営みを通じて、人間というもの、民族、そして神とは何か、宗教とは何かという深淵なテーマに迫っていることだ。簡潔でわかりやすい文章で。
イスラムでは、たとえば豚肉を食べてはならないし、牛や羊にしても、アッラー以外の名を唱えて殺された動物の肉は食べてはならないという。
なぜ人は食べることに神の許しを得るのか。キリンは自然に草を食うのに、なぜ人間だけは、食べることに禁忌があるのか。
その問いに対して、著者は「われわれ」という言葉を使う。
「われわれ」イスラム教徒はだれと異なるのか。いったい「われわれ」はだれから識別されるべきなのかという問題である。結論からいってしまうと、明確な他者が身近に存在すればするほど、「われわれ」という意識は先鋭化する。食に置き換えれば、「われわれ」にとっての正しい食が、よりはっきりとした輪郭をとることが求められるのである。
イスラム教、キリスト教、ユダヤ教は、中東で生まれた同じルーツを持つ宗教だけれど、「同じ啓典を授かった民」でありながら、たとえばイスラム教は豚を禁忌とし、ユダヤ教はタコやイカ、ウナギを禁忌とする。それには、上記のような理由があるのだろうと納得させられる。
さらには、現代も続く食の施しを通じたイスラムという教義への考察、そして共食への考察。
日本という国にいて、イスラムという国の戒律の厳しさを思う。けれども、この本を読むと、むしろイスラムという宗教の慈愛と豊かさが印象に残る。
日本人は雑食といわれるけれども、近世まで牛は食べなかったし、外食は男性の文化だった。何を神から授けられた糧とするのか。その立ち位置で、食文化は変わっていく。
それぞれの民族が、それぞれの神を持ち、それぞれの食文化を育み、その中で分かち合うことで、共生の社会が生まれる。そんなあたりまえの多様性を思い知らされる。


