経営における編集者の役割、クリエイティブディレクターの役割
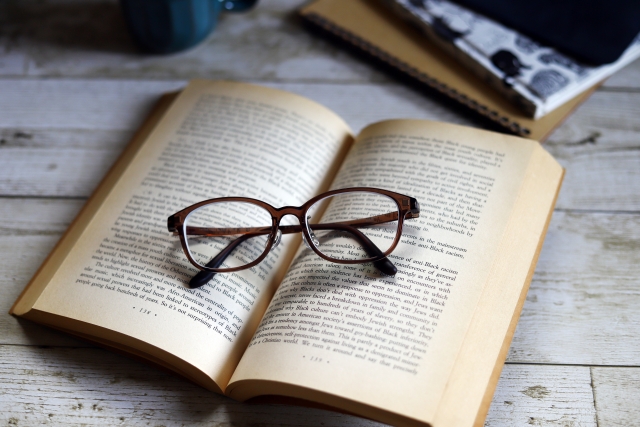
訪日外国人向け WEBメディア「MATCHA」を運営する青木優さんの「編集者兼秘書、という仕事が増えるかも。」というブログが面白くて、この何日か、ずっと考えている。
コルク佐渡島庸平さんは、ご自身の事業を通じて「作家の頭の中をパブリッシュする」といっておられる。
同様に「経営者の頭の中をパブリッシュする」という役割がたぶんあるのだろう、と最近思う。
それは、これまで広報という位置付けだったかもしれない。経営者の強烈なビジョンを言語化し、発信していく。
発信するためのツールは、既存メディアかもしれないし、ソーシャルメディアだったり、あるいはオウンドメディアを作るということも含まれるのだと思う(ちなみに最近、自社でカンファレンスを開催する会社が増えているけど、これもまた、オウンドメディアのひとつの流れだと思う)
強烈なビジョンを具現化する、ということは、そもそも経営という営みそのものかもしれない。
ただ、事業運営とは別に、経営者と伴走して、言語化する。編集する。最も訴求力のある言葉を、訴求力ある形で、世に出していくという仕事。
たとえばピーター・ティールの「空飛ぶ車が欲しかったのに、手にしたのは140文字だ」という言葉は、強烈で、この経営者の世界観を見事に象徴して、人を揺さぶり、新しい世界へと誘う力さえ持つと思う。
で、やや話は飛びますが、クリエイティブディレクターの仕事が、経営に近づいているという事象も面白く思う。
有名なのは、佐藤可士和さんがセブンイレブンのブランドリニューアルを手がけたやつとか。会社のコンセプトや方向性まで入り込んで、形にして、発信していく。会社そのものを「編集」する仕事。
編集であったり、クリエイティブというものが、経営において果たす役割が、徐々に変わっているのかも、と最近思う。それは、トップの役割が、ヒエラルキー型組織のマネジメントから、ゼロからものを生み出すことに回帰しているからかもしれない。
その言語化、会社を編集するということに、いろんな可能性があり、働き方がありそうだなと思っている。

